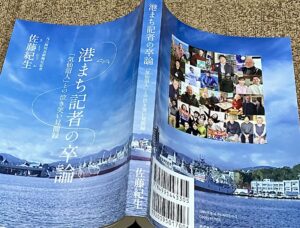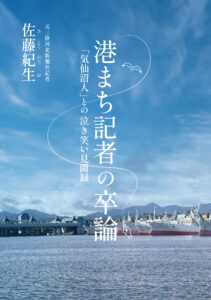気仙沼市の景勝地の中には、今から約2億8千万年前の古生代ペルム紀に生成された石灰岩および、その後の火山活動によって火成岩が入り込み、熱によって大理石となった地層が織りなす地形がある。
潮吹岩で知られる「岩井崎」をはじめ、唐桑半島随一の観光地である「巨釜・半造(おがま・はんぞう)」などが代表的だ。
白く輝く大理石と、浸食などにより黒っぽく変色した石灰岩との対比と、自然が「彫刻」した景観が、青い海と空との見事なコントラストを描く。
その中でも、個人的にお勧めしたいのが、その名もずばり「大理石海岸」。掲載した写真は2枚とも今月5月5日に撮影した。まさに新緑のころ、湾の奥には緑色、そして沖合には青さを増した海が広がる。
そこに、まるで庭師が配置したかのように白く輝く大理石が並び、松の緑が彩りを添える。規模的には決して大きくないが、海の「盆栽」とでも言うべき見事な景色がそこにはある。対岸には岩手県陸前高田市の広田半島が見える。
大理石海岸があるのは気仙沼市唐桑町岩井沢。仙台、気仙沼市中心部方面からだと三陸道「唐桑小原木インターチェンジ(IC)」を下りて、すぐ南側にある。旧・小原木小から「岩井沢漁港」へと続く坂を下ると、そこに小さな無料駐車場がある。駐車場から、写真のある景観を望む場所までは1分も掛からないで行ける。
大理石といえば、ギリシャのパルテノン神殿、ローマのコロッセオ、インドのタージ・マハルなどの建造物が有名だ。彫刻作品では「ミロのヴィーナス」、そしてミケランジェロの「ダビデ像」もそうだ。大理石は英語で「マーブル」。渦巻きや細い線が幾重にも重なり、それらが織りなす斑(まだ)ら模様と、磨き上げた大理石の光沢は美しく、古代より珍重されてきた。
元々はサンゴ礁からできた石灰岩なので、大理石の表面をよく観察すれば「ウミユリ」などの化石が見つかる。実際、「大理石海岸」の岩々からも発見されている。

写真の2枚目は、1枚目の写真を撮影した場所から、岩井沢漁港の南側へと移動し、そこから狭い踏み分け道を進むこと5分。こちらも大理石からなる海岸がある。が、写真のように長方形の大理石が、幾つもある。
実はこれは切り出されたもので、ここは「石切場」。気仙沼市と合併する前の「唐桑町史」には、明治期に大理石が切り出された—との記述がある。
1907年(明治40年)、東京帝国大学の桜井定太郎教授とアメリカの鉱山学者であるR・スミス氏が訪れ「イタリア産の大理石をしのぐ」と絶賛した—とある。
3年後の明治43年には浅野セメントの創始者である浅野総一郎氏が産出に乗り出したが、経営上の問題から、わずか5年で休業。そのため切り出した一部が、そのまま現在も放置されたままとなっている。
写真撮影のために東日本大震災後、初めて訪ねたが、ほとんどが流失を免れていた。
切り出された大理石は、東京・日本橋三越本店正面玄関に設置されている2頭のライオン像の台座になったと伝わる。現在は花崗岩に代えられているが、唐桑町には古くから初代台座は「唐桑産」として言い伝えられてきた。私が地元新聞記者時代、今から35年以上前になるが、三越側の社史に「宮城県唐桑村産」という記述があり、確証を得た。「論争に終止符」との記事を書いた。個人的には、自身の取材を信じたいところだ。
余談だが、唐桑半島随一の景勝地と書いた「巨釜・半造」。双方が隣接しているが、「巨釜」側にある「折石(おれいし)」は、高さ16m、幅3mの石柱で、天を衝くようにそびえる大理石の奇岩だ。元々の名前は形状から来ている「ろうそく岩」だったが、1896年(明治29年)の明治三陸大津波の直撃を受け、その先端部が約2m折れたため「折石」と呼ばれる。
その名前の由来が大津波だったと言うのは、ある意味、何度も何度も津波被害を受けてきた三陸沿岸の象徴でもある。そして、今回の東日本大震災には耐えた。その希望の大理石の石柱でもあるのだ。
日本はどこの地方にも隠れた名所や、いわくのあるシンボル、歴史を知る場所がある。よく知られた景勝地とは違う、ひっそりと、しかししっかりと、その土地に佇む、まさに自然体の良さを、訪ねるのもいいものだ。