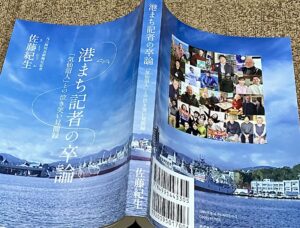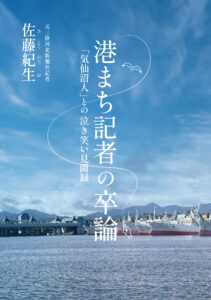サンマ。
カツオと並んで気仙沼港の水揚げを支えてきたサンマ。秋、魚市場はサンマと、戻りガツオの水揚げで賑わう。
その殺気立つような、湧き立つような水揚げラッシュは、地元記者をしていた私にとっても、気仙沼港が一年で一番、活況を呈する、その空間に身を置く喜びを与えてくれた。
そのサンマ。ここ数年は不漁が続いている。量も少なければ、魚体のサイズも小さい。昨年、気仙沼で水揚げされたサンマ。佐藤家の食卓に載った塩焼きは、まさにイワシサイズ。大ぶりで脂の乗り切ったイワシの方が、よっぽど大きい―と感じさせるもので、毎年、何匹ものサンマを食べてきたが、とてもわびしいものを感じた。
今年も、今のところ(9月中旬現在)、決して豊漁ではない。それでもサイズは幾分、ましになった。食したのは130gほどと、大ぶりと言える150g超とはいかないものの、脂もそこそこ乗り、塩焼きサンマならではの香ばしさ、うまみに満足した。
庶民の魚の筆頭は、イワシ、サバ、アジ、イカなどと並んでサンマが五本指に入るだろうか。
西日本となると、違う魚がランキングに入るであろうが、東日本では上記でほぼほぼ間違いないと思う。
最近は養殖ギンザケは、サーモンとしてすしネタとしても人気で、それも入れるべきかもしれない。
そのサンマ。北海道沖が主漁場だ。かつては三陸沖に大きな漁場が形成されていた。気仙沼港は昭和30年代には、水揚げ日本一に君臨することも多かった。鮮魚出荷以外にも、加工も盛んに行われ、その煮汁が閉鎖的な気仙沼湾に捨てられることで、赤潮が毎年発生するーそんな公害まで起きていた。
サンマを満載したトラックは、曲がり角などでサンマを落とし、それを拾って夕食にするーなんていうのも日常茶飯事だった。
私が、気仙沼テレビ放送(現・気仙沼ケーブルネットワーク)で働き始めた昭和50年代後半でも、盛漁期には1日で1000トンを超す水揚げが続く日がたびたびあった。
人口6万人の小さな、東北の漁港が1日に1000トンものサンマをさばく力があることに、驚いたものだ。
気仙沼漁港には、最も大きな遠洋マグロはえ縄船をはじめ、カツオ一本釣り船、巻き網船、そしてサンマ船が並ぶ。サンマ船の特徴は、なんといっても、まるでトンボの羽根のような板状のものが何本も並ぶ。これはLEDライトからなる「集魚灯」だ。
かつては白熱電灯で、近寄るだけで、その熱量に驚いたものだが、現在のLEDは涼しげに青みがかった光を放つ。
サンマ船の漁法は、その光を利用した「棒受け網」という特殊なものだ。サンマは光に集まる習性がある。イカ釣りも電灯をともし、夜に行われ、気仙沼湾でも夜、海に点々と浮かぶ「漁り火」が見える。
サンマ漁も夜に行われる。その漁法は長年の間に改良が加えられ、極めて効率的かつ、集まったサンマがお互いに魚体を傷つけ合うのを防ぐ工夫が凝らされている。
そのサンマ棒受け網漁は、こうだ。
①まず魚群探知機やサーチライトで群れを探す
②LED集魚灯を船の左右いずれかの一方だけ点灯させ、群れを集める
③群れが集まった、反対側に2本の棒にくくりつけた網を広げる。そして魚が十分に集まった頃合いを見て、集魚灯をとも(船尾)の方から順次、消灯。その代わり、仕掛けた網の方の集魚灯を一斉点灯する。するとサンマは仕掛けた網側に移動
④移動を終えたら、すかさず網を手繰り寄せ、サンマをすくい上げるように捕獲するー。
群れを集めるのに餌を投入すると、サンマが餌を求めて激しく動き、サンマ同士がぶつかり、魚体を傷めるが、光を利用することでサンマを興奮させず集めることができる。さらに一網打尽という効率的かつ迅速な漁獲ができるのだ。
一般に130g以上が大型。150gを超えれば脂の乗りも最高で、そのうまさは絶品だ。家のガスコンロで焼いても十分にうまい。が、やはり炭火焼きは絶品だ。佐藤家でも、かつて七輪に炭をおこし、炭火焼きをしたことがある。まずもうもうと立ち上る煙がものすごく。それは近所迷惑になりかねない有様だった。それに炭火で脂の多いサンマを焼くのは、素人には無謀と言えた。皮は真っ黒に焦げ、しかし中の身は生焼けということもあった。
その後、壁やガラス窓に染み付いた油分を含んだ煙は、酸化した後、あまり芳しくない匂いとして長く残るという弊害も出る。
それに懲りて、家庭での炭火焼きは断念している。
気仙沼市内には、炭火で焼き魚を食べさせる名店がある。秋に毎年、気仙沼市魚市場を会場に開かれる「気仙沼産業まつり」と同時に開催される「市場で朝めし。」では、炭火焼きの職人たちが、うまみを逃さず、こんがりと焼き上げたサンマを食べることができる。
落語の「目黒のさんま」にヒントを得て、毎秋、気仙沼港から新鮮なサンマを運び込み、市民に振る舞う「目黒のさんま祭」で培ってきた炭火焼きの技術を遺憾なく発揮。塩焼きサンマの極意を味わうことができる。
今年の開催は、まだ正式には決まってはいない。どこまでサンマ漁が回復するかによるのだろう。
地球温暖化の影響で、各地で水揚げされる魚の種類も変化している。自然が相手とはいえ、気仙沼の代名詞であり続けるサンマとカツオ。是非とも、主役に留まってくれることを願うばかりだ。
気仙沼港で水揚げされたサンマでなくとも、今年のサンマは十分においしい。秋の味覚をぜひ味わってほしい。