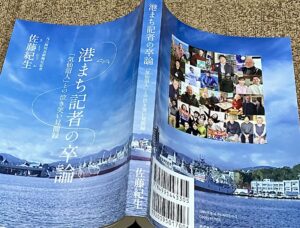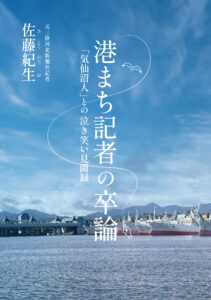気仙沼市の「ゆるキャラ」と言えば、文句なしで「海の子 ホヤぼーや」。
その名前の通り、三陸地方の夏を代表する海の幸、養殖で栽培されるホヤから生まれた「海の申し子」。頭の形が「海のパイナップル」と称されるホヤの色とゴツゴツしたこぶと、そして角のように飛び出る突起の先に「➕」と「➖」の切り込みがある。実はこれ、「➕」の方が「吸水孔」。海水を吸い込み、その中にいるプランクトンを摂取する、私たちの鼻と口の役割を果たす。そして「➖」は「排水孔」。プランクトンや栄養分を濾(こ)し取り、不要なものを捨てる出口だ。
この形が目立ち、子どもたちにも「➕」「➖」の形がすぐ分かるので、「ホヤぼーや」のキャラクターにはピッタリの特徴と言えるかもしれない。
気仙沼地方は、石巻に次ぐ全国有数のホヤの生産地である。新鮮で栄養たっぷりな海水を、ごくごくと旺盛に摂取し、すくすくと育つ。「海のミルク」と称されるカキと同様、腐葉土が培った森の恵みを、川を通じて受け取った豊穣の海が育てた、まさに「海の子」。身は鮮やかなオレンジ色。そして、その味は「海の精」をギュッと凝縮したような濃厚な旨味、そして鼻腔をくすぐる潮の香。日本を代表するフレンチレストランのシェフで、気仙沼で子どもたちを対象に毎年開いている「プチシェフ・コンテスト」の審査委員長を務める三國清三さんは、北海道育ちで、幼少の頃からホヤを食べてきたという。「ホヤには、いわゆる五味『甘味、塩味、酸味、苦味、そして旨味』が全てそろう。ホヤが私の舌を鍛えた」と話す。
東北・北海道、しかも沿岸部以外では、長らくホヤは「珍味」の域に留まっていた。理由は、鮮度落ちの早さだ。今から50年近く前、東京の居酒屋で、「三陸産ホヤ」というメニューがあり、早速、注文したが、「こりゃダメだ」とうなだれた。美味しくないとまでは言えないが、奥に潜む「臭み」が全てを台無しにしていた。当時は冷凍(解凍を含む)・冷蔵技術が今と比べものにならないくらい低かったのだろう。今ではきちんと冷蔵、冷凍されたホヤは生と遜色ない(いや、私のような素人には味の違いは分からない)のだが、当時は「鮮度が命」とため息をつくしかなかった。
好みがあろうが、ホヤは酢やレモンのしぼり汁など酸味との相性がいい。王道だがシャキシャキのキュウリの添え切りと酢醤油、控えめのワサビで食べるのが最も好みだ。そしてホヤを食べた後に飲むビールはなぜか甘い。まさにマジック・フルーツならぬマジック・シーフード。「ホヤ酢」で生ビール。気仙沼の居酒屋の極上メニューだ。
ついホヤの話だと、そちらに夢中になってしまう。今回は「ホヤぼーや」の方が主役だった(笑)。実はホヤは、意外と人間に近い動物なのだ。同じ脊索(せきさく)動物であるが、人間を含む哺乳類から魚類が脊椎動物、このほかにナメクジウオなどが頭索(とうさく)動物、そしてホヤは尾索(びさく)動物に分類される。ホヤは幼生期には脳を持ち、活発に動き回るのに、成体になると脳は退化し、岩などに付着、そこに留まり、一生を過ごす。
なぜ、そういう「進化」をしたのかは不明で、現在も研究段階だという。そうした謎に包まれた生き物なのだ。
そのホヤから産まれたのが「ホヤボーや」。
いずれにしても気仙沼を含む三陸を代表する夏の味覚ホヤ。その化身が、気仙沼市の観光キャラクター「ホヤぼーや」なのだ。腰にはホタテ貝をバックルにしたベルトをきりりと締め、そしてサンマの刀で「災い」を退ける。笑顔がかわいい男の子だ。
「ホヤぼーや」が誕生したのは2008年。JR東日本が仕掛けた観光キャンペーンで、気仙沼市を代表する「観光大使キャラクター」として市民公募により生まれた。当時から、その愛らしい姿、にこやかな表情が人気だ。特に子どもたちは大好きだ。等身大の「ホヤぼーや」は各種イベントに引っ張りだこで、手を振ったり、子どもたちと握手したり、ハグしたり、大活躍する。
このほか様々なグッズや菓子類のパッケージやデザインに取り入れられ、今や気仙沼の「顔」と言っていい存在となった。「くまモン」や「ふなっしー」など全国区的な人気者ではないが、東日本大震災後、多くのテレビ関係者や映画監督らが、小物の一つとして取り入れ、画面はスクリーンの片隅に「ちょこん」と居たりする。
私も小銭入れや、キーホルダーにひっそりと「ホヤぼーや」が潜んでいる。いい年こいた大人が、ぬいぐるみを持っているのは、やや照れ臭い。照れ隠しに、孫へのプレゼントとし、一緒に「ホヤぼーや」と過ごす。そんな日常は悪くはない。ニコニコと笑う「ホヤぼーや」の笑顔に癒される。気仙沼に来た際は、ぜひお土産として、お持ち帰りいただければ幸いだ。